 視察から一か月たってしまいましたが、7月に視察した報告の続きです。
視察から一か月たってしまいましたが、7月に視察した報告の続きです。
尾道市内の急性期3病院と開業医との本格的な医療連携と他職種連携の地域ケア「尾道方式」について、数年前まで市民病院の看護師さんで、退職後、訪問看護事業所及び居宅介護支援事業所を運営し、医療と介護の連携を実践しておられる魚谷さんから,7日夜お話をお聞きしました。8日は尾道市民病院の「地域医療連携室」のかたからお話をお聞きしました。
患者さんが医療や介護や終末期医療をどこで受けたいのか、その人の希望する生活を組み立て,家族支援も行う。そこから出発した事業で、元医師会長の先生の強力なリーダーシップのもとで進められてきたとのことです。
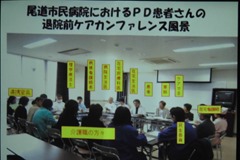 尾道市民病院には、入院前から入院期間にかけて在宅を見据えた看護ケアに取り組み、スムーズな在宅支援につなげるために、「在宅支援看護師」が配置されています。この「在宅支援看護師」は「医療連携室」とともに、院内における看護連携を強化するために外来、病棟に配置され、月に1回ミーティングをしています。
尾道市民病院には、入院前から入院期間にかけて在宅を見据えた看護ケアに取り組み、スムーズな在宅支援につなげるために、「在宅支援看護師」が配置されています。この「在宅支援看護師」は「医療連携室」とともに、院内における看護連携を強化するために外来、病棟に配置され、月に1回ミーティングをしています。
そして「退院前カンファレンス」を他職種恊働で開催。市立病院側からは患者さんの主治医、看護師、薬剤師、栄養士、リハビリ臨床心理士、透析ナースなど。在宅でケアする側からは、かかりつけ医師、訪問看護師、ケアマネージャー、訪問介護、通所介護、通所リハビリ、福祉用具の事業者などと一緒に患者さん、ご家族も参加されます。
患者さんやご家族の思い、どういう医療と介護をうけたいのか希望を聞き、不安についてもひとつずつ具体的な手だてをとりプランをつくり医療と介護の連携をどう進めるのかを相談します。ケアのポイント、緊急時の対応などについて共通認識をもつことができる。患者さんやご家族にとって在宅を支えるチームを知ることで安心感をえる事が出来、また病院スタッフと在宅チームとのコミュニケーションを促進できるとのことです。
必要な医療ケアは何か、誰がそのケアを行うのかを明確にし、確実に在宅生活につなげられる。結果的に在院日数が短縮化されるということです。
 尾道方式は患者さん中心に、これだけの専門スタッフが支える事で、病院から在宅へ、安心してつなげる事が出来るんだと思います。
尾道方式は患者さん中心に、これだけの専門スタッフが支える事で、病院から在宅へ、安心してつなげる事が出来るんだと思います。
7月に強行採決された『医療・介護総合方法』は、先に退院ありき。先に在院日数削減ありきだと思います。退院させられても、在宅で受ける医療や介護の基盤や体制、しくみが不十分な今のままでは、医療や介護の難民が生まれてしまうのではないでしょうか。