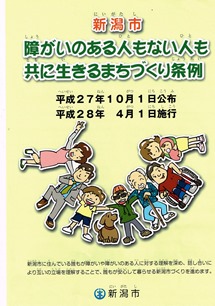 国は、平成25年6月に障害者差別解消法を制定し、いくつかの自治体で条例が制定されています。今回、新潟市の視察のポイントの1つがこの差別解消条例です。
国は、平成25年6月に障害者差別解消法を制定し、いくつかの自治体で条例が制定されています。今回、新潟市の視察のポイントの1つがこの差別解消条例です。
新潟市は、平成20年に障害者権利条約が国連で発効した同じ20年の9月議会で、すでに新潟市独自の障がい者の条例の制定について市議会で質疑され,平成25年4月には「(仮称)障がいのある人もない人も一人一人が大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会」を設置するなど、国の差別解消法の制定以前から取組まれてきたことがわかりました。
基本理念 「全ての市民が、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、話合いにより相互の立場を理解すること」としています。
この「話合いにより」が、この条例のポイントですと担当者の説明でした。
市の責務は 「この条例のめざすべき社会を実現するための施策を推進すること」としています。
次に「市民・事業者の役割」 として、「理解を深めるとともに、障害のある人に対する差別を解消する取組を市と一体となって行なうよう努めること」としています。責務にしないで役割としたとの説明でした。
条例で禁止している事項
これが条例の核となるとのことですが、「市・事業者に対して、福祉サービスや医療など9分野における差別(不利益な取扱・合理的な配慮の不提供)を法的義務で禁止」としています。
差別解消法が努力義務としていますが、新潟市の条例は法的義務とした理由は法的義務なら話合いに応じてくれるだろうと判断したとのこと。
合理的配慮の不提供について
「障がいのある人から何らかの配慮と求める意思の表明があった場合(意志の表明が困難な障がいのある人の場合は、その支援者から求めを含む)としていますが、新潟市の条例は、続けて、「又は意思の表明がなくても障害のある人に何らかの配慮が必要なことを認識しうる場合に、その人の人権・意向等を尊重して、社会的障壁を取り除く変更や調整をしないことをいいます」としています。この下線の部分は、条例検討委員会に参画している新潟県弁護士会からの要請で盛込んだとのことです。差別解消法を上回る規定が設置されているのです。
未然の防止策 として障害のある人に対する差別の解消に向けた協議提案を行なう「条例推進会議」を設置。
差別の事後対策として
1、障害種別・内容を問わずに対応する「相談機関を」を設置。
2、助言・あっせんの必要性について建議する「調整委員会」を設置する。
3、条例の実効性を確保するため「助言・あっせん・勧告・公表」を規定。
条例推進会議も調整委員会も当時者団体の代表の方が参画されています。
条例の特徴は
1、 差別を法的義務で禁止していますが、話合いによる解決をめざします。
2、 バリアフリー化などの環境の整備については、合理的配慮と分けて位置づけています。
3、 罰則は規定していません。
川崎市は、差別解消法にもとづく条例を制定するのでなく、対応要領を示しています.今回新潟市の条例は大変勉強になりました。